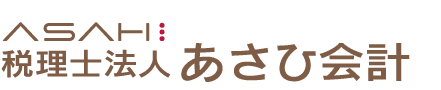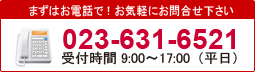世界中がトランプの言動に振り回され、戦々恐々としている。そもそも日本のメディアは今回の米大統領選は接戦で、ハリスが若干有利だと報じていたのだが、選挙人数では312人対226人でトランプが圧勝、一般投票数でも74百万票対71百万票とトランプがハリスを3百万票上回った。
世界中がトランプの言動に振り回され、戦々恐々としている。そもそも日本のメディアは今回の米大統領選は接戦で、ハリスが若干有利だと報じていたのだが、選挙人数では312人対226人でトランプが圧勝、一般投票数でも74百万票対71百万票とトランプがハリスを3百万票上回った。
トランプ支持の背景には何があったのだろう。
➀ 不法移民の受入。バイデン政権が不法移民を無制限に受け入れたため治安が悪化し、かつ、一般市民の仕事を不法移民者が奪うという事態が数多く見受けられ国民の怒りをかった。
➁ インフレの深刻化。トランプ1期目はインフレ率 2%台、失業率 3%台、実質経済成長率3%台と理想的な経済状況だった。それがバイデン政権4年間の平均インフレ率は5%弱となり中間層以下の生活を圧迫した。米国人の豊かさとは、高卒で製造業に携わり、定年まで働き、住宅を一軒持ち、子供を 2 人育て大学に行かせることだったという。そんなアメリカンドリームがここ 20~ 30 年で崩れ去っている。だからトランプは米国における製造業の復活を第一に考えている。
➂ 言論統制。米ソーシャルメディア大手は連邦政府の抑制圧力により偽誤情報対策としてトランプのアカウントを凍結したのだが、このままでは米国は検閲国家となり言論の自由が失われるとイーロン・マスクをはじめ多くの知識人がトランプ支持に回った。
今回の米大統領選挙は保守と革新との対決というよりは市民レベルの常識(EV も良いけどガソリン車も良い、性転換を学校で教える必要はない等)の是非を問う戦いだったとも言われている。
それでは第 2 期トランプ政権はどのような政策を打ち出してくるのだろう。第 2 次世界大戦後の世界は他の諸国を凌駕する圧倒的な経済力と軍事力を背景にした米国の覇権下にあった。
米国は政治的には自由民主主義、経済的には資本主義の普遍性を掲げて世界を主導してきた。
しかし米国は覇権を維持するために、軍事同盟と自由貿易秩序のための多額の負担を強いられてきた。トランプから見れば軍事同盟も自由貿易も米国への「ただ乗り」であり、米国の利益を損なうものに過ぎない。ヨーロッパ諸国も日本も韓国も米軍駐留経費引上げや自国の防衛予算の増額圧力が加えられるだろう。また、莫大な貿易赤字を出しながら自由貿易を維持することは、自国の競争力の乏しい産業を犠牲にすることであり公正とは言えない。トランプは中国だけではなく同盟国に対しても関税引上げを強行するだろう。
関税を上げればアメリカではインフレが進む。
だが一方でトランプは「Drill,baby,drill」とシェールガスの採掘をけし掛けている。これまでは環境問題を配慮し規制していたが、掘りまくれば米国は世界最大のエネルギー産出国となる。米国民にとってはガソリン、牛肉、牛乳が体感するインフレ感のトップ3だが、ガソリンの値段が下がれば国民のインフレの肌感覚としては問題なしだ。
またトランプはグリーンランドを買収する、パナマ運河を返せとも言っているが、それなりの理屈がありそうだ。グリーンランドは資源的にも軍事的にも重要だが、中国はデンマークが気付いた時にはグリーランドの土地の2割を購入しており、政府が慌てて契約を破棄した経緯がある。またパナマ運河は米国が切削し90年間にわたり運営していたが、カーター政権の時にパナマのために安価に譲った歴史がある。にもかかわらず、現在は運河の重要なインフラの支配権を中国が握っている。
とはいえトランプはあまりにも短絡的だ。アメリカ第一主義を掲げ、パリ協定からの離脱やWTO からの脱退をほのめかす等、覇権から自発的に撤退しようとしている。しかし、単発的なディール1つ1つの利益最大化では長期的安定は得られない。