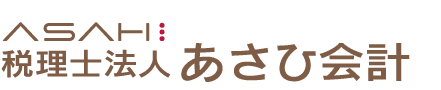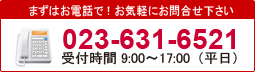大卒初任給 30 万円時代がやってこようとしている。2025 年 4 月で大卒初任給 30 万円超の会社は事業所全体の 1.7% に過ぎないが、現在 1,055 円(全国平均)の最低賃金が 1,500 円の時代になると大卒初任給は 30 万円になると言われている。
政府は最低賃金 1,500 円を 2029 年までに達成する目標を立てている。2025 年度の大卒初任給は全国平均で 224,888 円(東北エリア平均で 205,628 円)だから、あと4年間で全国平均で 75,112 円アップしていかなければ初任給 30 万円に追いつかない。
東北地方の地銀の大卒初任給を比較してみた。

勿論、初任給アップは既存社員の給与見直しも必要となってくるから財源の確保が必要だ。中小企業にとってはかなりの重荷だろう。とはいえ初任給アップの背景には、物価上昇への対応、人材確保、競争力向上などの要請があり、初任給アップに対応していかなければその企業は取り残されてしまうことになる。
最近、M&A 市場に出てくる企業の様相が様変わりしてきている。以前は大半が後継者不在企業のM&A による事業承継が目的だったが、最近の案件は親御さんが息子さんに事業を承継したあと、その息子さんが引き継いだ企業の将来をおもんぱかってその引継いだ企業を M&A 市場に出しているのだ。
つまり、40 歳後半で親から事業を引き継いだものの、よく見てみると従業員のほとんどが 50代から 60代、といって新卒は来てくれない、若い人の中途採用もままならない。5 年後この会社はどうなっているのかを考えるととても継続していく自信がないというのだ。
では中小企業の経営者はどうすればよいのか?
給料を上げて、新卒を採用するか若い人を中途採用するしかないのだ。それが出来なければ会社を売るか、畳むしかない。
賃上げ?そんな事が出来るのか?出来るのだ。
現在、東証プライムに上場している「魚力」という会社は、かつて 3 店舗で売上 3 億円(利益30 万円、賞与なし)の魚屋だった。各店舗の人時生産性 (付加価値 /総労働時間 )は A店 2,000円、B 店 2,500 円、C 店 3,000 円、全店舗の加重平均は 2,600 円だった。生産性を上げるには労働時間を短縮するか、付加価値を上げるしかない。
どうすればよいのか?
魚力の経営者は人時生産性の最も高い C 店がやっている業務を可視化して、それを全店舗で共有化すれば全店舗の人時生産性は3,000 円に出来ると考えたのだ。調べてみると C店では最も利益率の高い「刺身の盛合せ」を大量に販売していた。「刺身の盛合せ」は作るのに手間がかかり現場の社員が嫌がる商品だった。C 店では、これまで職人だけしか作っていなかった刺身の盛合せを作り方を工夫してパートでも作れるようにしていたのだった。こうして各店の良い取組を全店で共有化していったところ、16 年間で人時生産性は 5,600 円までになった。当時 5,600 円という人時生産性はイトーヨーカ堂やダイエーよりも高かったという。
やっていることは決して難しくはない。成果を上げた時にやっていた業務は何か?それを全社で(あるいは毎日)実施すればよいのだ。
この発想をもとに人事制度を作ったのが ENTOENTO( 人事制度コンサル会社 ) の松本順市社長だ。松本社長は魚力に学生時代から関り、16 年間勤務したのち、「社員を物心両面から幸せにしたい」という経営者の思いを実現する人事制度を日本中に広めたいとコンサルタントに転身した。人時生産性 2,000 円と 3,000 円の違いは何か?「やる気の違い」ではない、「能力の違い」でもない、「やっていることの違い」だ。人時生産性を高めれば、賃上げの原資が確保され、人材を採用し、企業を存続させる事が出来る。