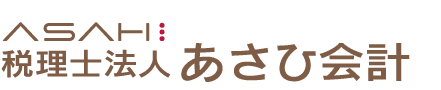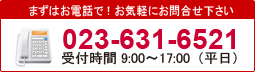日経新聞に連載されている『私の履歴書』の 10月版は元サッカー日本代表監督岡田武史氏の履歴書だった。岡田氏は、「FC 今治」の運営だけではなく地域創生や人材育成事業でも活躍している経営者だ。彼はまた、京セラ創業者の稲盛和夫氏が主宰する経営哲学や人生哲学を学ぶ「盛和塾」の塾生だったので、塾長例会や世界大会でもお見掛けし、後に彼の講演を聞いて只者ではないと思っていたので関心をもって新聞の連載を拝読した。
特に 10 月 12 日に掲載された『指導者の原点』と題する記事には感銘を受けた。彼は、所属していたチームの成長が思うようにいかずドイツにコーチ留学をするのだが、ドイツでサッカーの高度な戦術を学べたわけではなかった。養われたのは指導者としての背景、原点のようなものだったという。ドイツで所属したチームの監督は「選手に好かれたい。いい人に思われたい」みたいな下心が毛頭ない。目的はただ一つ勝つこと。その為には孤独を受け入れる強さ、覚悟を持っていたという。岡田氏は「小善は大悪に似たり、大善は非道に似たり」という稲盛塾長の教えを引用し、選手にとって本当に必要な大善を成すには情を排し、鬼になることも時に必要だと述べる。留学から帰国後、「ダメなものはダメ、いいものはいいと区別する覚悟ができると物事の解像度がぐんと上り、びっくりするほど成果が出た」というのだ。
稲盛塾長は「信念もなく、部下にただ迎合している上司ならば、決して若い人たちのためにならない。それは若い人たちにとって楽だが、その気楽さは彼らをダメにしていくはずだ。長い目で見れば、厳しい上司の方が、部下は鍛えられ、はるかに伸びていく」というのだ。「短絡的に良かれとすることが、本人にとって本当に良いことなのかどうか、リーダーは、部下への真の愛情を見極めなければならない」と若手経営者である盛和塾の塾生たちに諭すのだった。
稲盛塾長は、この「小善と大善」という概念を最初から持っていたわけではない。塾長は一貫して、利他の心、優しい心、思いやりの心、純粋な心、美しい心を持ちなさいと説き、塾長自身も事業に対するチャレンジ精神と勇気を持つことと同時に、優しい心を持つようにずっと心掛けてきたという。
ところが、いざ事業を始めてみると、どうしても社員に小言を言わなければならない、時には厳しく叱責しなければならないこともあり、場合によっては「君は辞めてくれ」ということまで言わなければならない。社員に対して優しくしなければならないと思っていたのが、事業を始めた途端、たちまち矛盾に直面したというのである。これは、まさに自分のエゴではないのか、経営者になった途端、自分の会社を良くせんがために、これまで自分が抱いてきた人生観に反するむごいことを従業員に要求し始めた、いよいよ自分は悪の本性を現した、と思い非常に悩んだという。
そんな時に、IBM の社是に「従業員を大切にする」という項目があり、その説明に次のような話が出てくることを耳にしたのだ。
「ある北国の湖のほとりに、心優しい老人が住んでいて毎年飛来してくる野ガモたちに餌を与えるようになりました。くる年もくる年も老人は餌をやり続け、野ガモもその餌を越冬の糧にするようになりました。ある年もまた、野ガモの群れがその湖にやってきましたが、老人は現れません。老人は亡くなっていたのです。その年、寒波が襲来し、湖は凍結してしまいました。老人を待ち続け、自分で餌をとることを忘れてしまった野ガモたちは、やがて皆餓死してしまったのです。」
そして「IBM はそのような社員の育て方はしない」と書かれている。稲盛塾長は「これが真の愛情だ」と気が付き、その後仏教の教えに「小善は大悪に似たり」という言葉があるのを見つけ「これだ!」と会得し、大善を実践していくことになるのである。