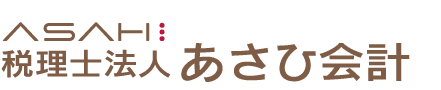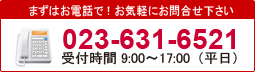トランプ関税に対するトヨタの対応が注目されている。2025 年 4 月トランプ政権が輸入車(部品を含む)に最大 25%の追加関税を課すと宣言したことで世界の自動車メーカーは厳しい状況に追い込まれた。しかしトヨタは営業利益 1 兆4千億円 ( 関税15%を想定 ) の押し下げが想定されているなかで、「場当たり的な価格転嫁はしない」として顧客や仕入先に丁寧に向き合おうとしている。又、トヨタは国内の人員整理につながる米国への生産移管をせず、国内の生産 300 万台体制を「揺るがず守る」と明言した。関税によるコストアップを原価改善や台数増で吸収してマイナスの影響を縮小する考えだ。
その結果、7月のトヨタの北米市場での販売は19.0%増で、過去最高となった。一方、トランプ関税を価格に転嫁した他のメーカーは、北米での販売が振るわず関税打撃で総崩れとなっている。
今般のトヨタの対応は日本的経営の神髄を象徴している。株主の利益を最重要視する欧米の株主資本主義のもとでは、不可抗力の関税によるコストアップがあれば業績の悪化を避けるために価格に転嫁するのは当たり前の話だ。価格を転嫁せずに業績が悪化すれば経営者は物言う株主達に経営責任を問われかねないのだ。株主の意向を気にする経営者は短期的利益を追わざるを得ない。
一方、日本的経営の原点には近江商人の「三方よし」の哲学があり、「売り手よし、買い手よし、世間よし」という考え方には、単なる利益追求ではなく社会全体との調和を重視する思想がある。トヨタも従業員、消費者、取引先、地域社会の利益に重点を置き、株主利益は後回しという考え方であり、短期的利益ではなく、長期的持続的成長を図るのが経営の本質だと考えている。
日本的経営の独自性は海外の有名大学でも研究され、評価されている。日本の企業は従業員を大切にし、従業員の現場力を尊重し、チームワークと長期雇用を軸にした経営を実践して成功している。日本企業には「人を育てることが企業の力になる」という信念があり、従業員を家族のように扱う経営スタイルに繋がっているのだという。現場からの改善を重視する「カイゼン」や、品質を最優先する姿勢も日本的経営の特徴だ。職人文化や細部へのこだわりが経営にまで浸透している。
フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップを傘下に持つメタ社のCEOで34兆円の資産を持ち、世界第 3 位の富豪マーク・ザッカーバーグは最近日本文化に感化され、経営を変革している一人だ。
シリコンバレーではスピードを重視するため「完璧は善の敵」という格言があり、完璧主義文化の日本とは正反対の思想がある。当時メタ社の翻訳システムは業界最高水準を誇っていたが、「忖度」という概念の翻訳問題に取り組んでいた日本人エンジニアは、単純な単語対応では限界がある、「日本のユーザーの期待に超えなければならない」として、文化的背景や人間関係まで考慮する「空気を読む」概念を AI に学習させ、翻訳精度を劇的に向上させたのだ。彼の祖父は漆器職人であり、祖父から受け継がれた「見えないところで完璧を追求する」という哲学はザッカーバーグに衝撃を与えたという。
その後日本を訪れたザッカーバーグは刀鍛冶の工房で 1 時間以上無言で鋼を打続け、京都の禅寺で座禅を体験して「何もしないことで、すべてを成し遂げる」という「無為」の概念を学び、「自我を手放した時、初めて他者のために存在できる」という住職の言葉に人生観を根本から変えたという。
今、AI への過度な依存は人間の思考そのものを外部委託するリスクをはらみ、人類が思考や感情、他者との深いつながりを失う危険性が指摘されている。この問題の解決策としてザッカーバーグは AIシステムに意図的に不完全さを組み込み、人間的示唆を引き出す AI を作ろうとしている。この AI はユーザーの代わりにすべてを処理するのではなく、考えるきっかけを提供するものだ。答えを教えるのではなく、質問を投げかける。効率化するのではなく立ち止まって考える時間を作るのだという。