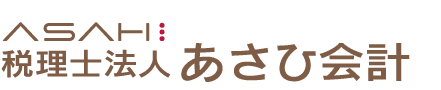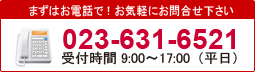日本の伝統芸能である「歌舞伎」を舞台とした映画『国宝』は 6月に公開されたが、100年に1度の芸道映画の傑作として大絶賛を浴びている。
第一印象としてはストーリーより演技のすばらしさ、映像の美しさに心を奪われ 3 時間は瞬く間に過ぎてしまった。主な配役として 3 名を上げるが他のキャストも超豪華な主演級の俳優陣で、物語を重厚に、そして熱くしている。〇吉沢亮(喜久雄)…任侠の一門に生まれ抗争で父を亡くし上方歌舞伎の名門花井半二郎(渡辺謙)に引き取られる。〇横浜流星(俊介)…花井半二郎を父に持つ御曹司で、喜久雄とは生涯のライバルであり、親友でもある。〇田中泯(万菊)…女形の人間国宝。喜久雄と俊介に “女形の凄み” を知らしめる。
これら主役級の俳優達は歌舞伎界の出身ではない。撮影に入る1年前から日本舞踊の稽古を始め、生まれながらの歌舞伎役者に見えるように、品格が滲み出るようにと稽古をつけられたという。日本舞踊は歩き方が大切で中腰になる必要があるが、グーッと腰を落として筋肉そのものを女形にしないと踊れないというのだ。
しかし、李相日 ( リ・サンイル ) 監督は最初から本職の歌舞伎役者を起用する考えはなかったという。歌舞伎を見せる以上に“歌舞伎役者の生き様”を撮りたかったからだ。身体表現としての歌舞伎よりも内面的到達点を、後に人間国宝になる喜久雄が生涯を通じて探し求めている “景色” を吉沢亮に託したともいえるのだろう。
映画『国宝』に対しては、市川團十郎や片岡愛之助などの本家本元の歌舞伎役者からも称賛の声が寄せられている。そして、これまで歌舞伎とは縁のなかった特に若者達の中に本物の歌舞伎を見てみたいとの関心が高まっている。
映画の中の歌舞伎の主な演目は次の通りだ。
「二人藤娘」…藤の花の精が松の大木に絡んで娘の恋心のさまざまをおどる。映画では俊介と喜久雄の息の合った踊りがドキリとするほど美しい。
「曽根崎心中」…遊女お初と恋仲の徳兵衛は友達に騙され金も信用もすべて失う。しかし証拠がない。潔白を証明するには死ぬしかないだろう、お初は「徳様の死ぬる覚悟が聞きたい~」と徳兵衛に迫る。映画では公演の直前に怪我をした花井半二郎は自分 ( お初 ) の代役として “血” ではなく “才能” を選択して息子の俊介ではなく部屋子の喜久雄を抜擢する。この喜久雄が演じるお初が身震いするほどの鬼気迫る熱演で引き込まれてしまう。
「鷺娘」…恋に破れて死んだ娘の精が、恋の恨みの有様を様々と舞い踊る。そして降り積もる雪の中で息絶える。映画の最終場面で人間国宝となった喜久雄が雪の中で白鷺のごとく舞い続けるのだが、芸のためにすべてを犠牲にした喜久雄が見た“景色” とは何だったのだろうか?
映画『国宝』は、私がこれまで見た映画の中で最も感銘を受けた映画だが、原作をはじめ、監督、脚本、俳優、振付、撮影など誰が欠けても成り立たない本当に奇跡のような作品だ。特に吉沢亮の絶賛の演技力は、自分を削ぎ落し女形になり切ることでいかんなく発揮され、横浜流星の全力を出し切るひたむきさ、伝統には背を向けてきた 80歳の田中泯の「どう生きてどう死んでいくのかを考える歳ですから」という覚悟の演技など、皆様にも是非見ていただきたい歴史に残る映画だ。
李監督はフラガールをはじめ数多くの受賞作品を出している在日朝鮮人 3 世で、51 歳だ。彼のデビュー作『青~ chong ~』は在日朝鮮人学校に通う高校生の青春の葛藤を描いた作品だが、その中に「日本では朝鮮人と呼ばれ、あっちに行けば日本人と呼ばれ俺たちは一体、何なんだろうな」というセリフがある。李監督は “血” という絶対的な隔たりを映画『国宝』でも主要テーマとして描いている。
代役でお初を初めて演じる喜久雄の様子を見に来た俊介に喜久雄は「震えが止まらない。俊ちゃんの血をコップでごくごくと飲みたいよ」と述べる。後継ぎは血なのか、才能なのか経営者も悩むところだ。