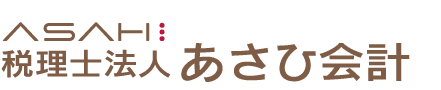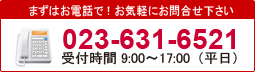世界で相続税のない国は中国、インド、ロシア、シンガポール、オーストラリア、カナダ、スウェーデン等々いくつもある。しかもアメリカなどは基礎控除が約 17 億円と非常に高く一般の人にとって相続税は無縁だ。日本の基礎控除は「3000 万円+600 万円×法定相続人の数」だから相続人が配偶者と子供 2 人であれば 4800 万円でイギリスの8000 万円、フランスの 1 億 4000 万円、ドイツの7000 万円と比べてもかなり低い水準だ。かつ、最大税率が 30%以上の国はフランス、イギリス、ドイツなど 8 か国(アメリカを含む)に限られるがその中でも日本は 55%とダントツだ。相続税は富の再配分の手段と位置付けられているが日本の相続税は世界一厳しいと言えるだろう。
しかも「法定相続制度」により権利が分散し、かつ「遺留分制度」( 遺言や贈与によって被相続人が財産を自由に処分することを制限する制度)と相俟って相続争いが多発し収拾がつかない事態になりつつある。当法人でも兄(姉)弟(妹)同士、母娘間等の争いなどで何件もの裁判を経験しているが、その結果、会社が潰れたり、兄(姉)弟(妹)同士や母娘が絶縁状態になったりと「争族問題」となっている。そもそも「相続」とは仏教用語で「相( すがた ) を続 ( つづける )」という意味であり、財産問題がメインではなく自ら生きてきた意味を次世代に伝えるのがテーマなのだ。
フランス民法に日本特有の「家制度」を加味した明治民法では、特定の家督相続人以外の者が財産を相続することは前提とされておらず、戸主(家督相続人)は配偶者や兄弟家族全員の扶養義務があった。つまり財産は「家のもの」であり、家の構成員はすべて同じ戸籍に入り、かつ隠居制度が存在し生前贈与 ( 贈与税は存在せず ) が認められていた。日本で相続税が導入されたのは1905年で、日露戦争の戦費調達のためだったが、税率は1.2%と超低率で生前相続が通常であった。
戦後の 1947 年アメリカ主導の日本国憲法とフランス法である従来の民法とのはざまで紆余曲折を経て現行の民法が施行される。英米法では「国民の財産に対して国家は口を出すべきでない」とし、大陸法では「国民の財産の行方は基本的に国家が決めるべきだ」としているが、アメリカに主導された日本国憲法では 29 条で「財産権はこれを侵してはならない」と英米法に倣い、一方、フランス法を基にした民法では法定相続主義を採用し相続に国家が関与しており、明らかに齟齬をきたしている。
財産の所有者(被相続人)が、自分の財産を遺言で誰に対して遺贈しても憲法で認められた正当な処分権の行使のはずなのだが、現民法では法定相続の配分に従って相続財産を分配することを前提とし、もし遺言によってその配分比率を崩した場合は遺留分侵害として法定相続分の半分までは請求することが出来ることになっている。作家で司法書士でもある河合保弘氏は、被相続人の遺産を国が勝手に配分することは憲法に照らして財産権侵害と言えないのか、公正と言えるのかと疑義を呈している。さらに河合氏は、現民法の「法定相続制度」や「遺留分制度」は GHQ が財閥解体や農地改革とともに日本の国力を弱体化させるための意図的な政策だったのではと考えている。
この「財産小分け」の問題は鎌倉時代に始まる。
二度にわたる元寇を撃退したのは鎌倉武士だったが、迎え撃ったのは主に二男、三男だったため功績の報償の要求に対して鎌倉幕府は所領を分け与えたという。この「田分け」が個々の武家の力を削ぎ幕府の滅亡につながったというのだ。現民法はまさに相続による「田分け」を推進して国民の財産を分散させ、かつ相続争いを多発させて日本の国力を削いでいると言えるだろう。
相続財産が相続税の対象となった人の割合は令和 4 年で9.6%だが、早期の相続税対策が必須だ。被相続人が認知症になってしまうと打つ手はない。