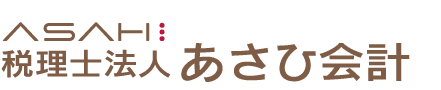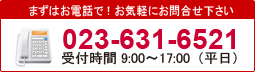あさひ会計の経営理念の 1 つに「私達は、質の高い仕事を通じ、顧客企業の継続発展に貢献します」という節がある。平たく言えばあさひ会計は「赤字企業は黒字に、黒字企業はもっと黒字に」するために支援を行うと宣言している。ではどうすれば「赤字企業が黒字に、黒字企業はもっと黒字に」なるのだろうか?
「赤字企業を黒字企業に」するにはドラスチックな改革が必要だ。現状を打破する必要がある。例えば➀赤字の得意先を切る、➁赤字の製品の生産をストップする、➂赤字店を閉鎖するなどだ。
例えば製造業であれば得意先ごとの P/L を作ることから始まる。得意先ごとの P/L を作ると必ず赤字の得意先があるものだ。しかも主要な顧客や優良な企業が赤字の得意先の場合が多い。当たり前の話だが、これらの企業は仕入先・外注先にも厳しいから優良企業になれたのだ。これらの得意先に対しては価格のアップをまずはお願いすることになる。価格アップがかなわない場合はその得意先から徐々に撤退するしかない。もちろん撤退と同時に新規顧客の発掘は必定だ。
製品 ( 商品 ) ごとの P/L を作ることも重要だ。
赤字の場合、売値の問題か、コストの問題かの吟味が必要だが、どうしても対応出来ないのなら止めるしかない。儲かっている仕事に注力すべきだ。
赤字の店についてはその要因が掴みにくい。立地なのか、商品なのか、オペレーションなのか、試行錯誤を繰り返しても業績が好転しないのなら撤退するしかない。コンビニでは商品ごとに交差比率 (=粗利率 × 回転率)を測定しており、一定の指標を下回った場合はその商品は棚から排除されるがその考えと同じだ。
これらの施策を実施すると売上が減るが、固定費をカバーする必要はあるものの利益が増えることになる。つまり、赤字企業の黒字化は「減収増益」の過程を辿ることになる。
「黒字企業をもっと黒字」にすることは一定の構造内の改善と考えられ MQ 会計を利用するのが効果的だ。
MQ 会計的にいえば ➀P( 販売単価 ) を上げる、➁V( 仕入単価 ) を下げる、➂Q( 販売数量 ) を上げる、➃F( 固定費 ) を下げることが黒字化の手段となる。 この MQ 会計的アプローチを行う上で必須なのがその企業にとって「Q」は何なのかということであり、その数値を毎日毎日捉えているかということになる。飲食業や小売業で言えば「客数」が「Q」であり、毎日毎日顧客数を捉えていなければ経営改善は行えない。それが時間帯ごとであったり、男女別であったり、年齢別であれば経営改善のアプローチに大いに役立つ。
MQ 会計によって前年対比を行うとその企業の利益構造が見えてくる。前年比で P( 販売単価 ) が〇%上がったので利益が ×× 百万円増えて、V( 仕入単価)が〇%上がったので利益が××百万円減少した。
Q( 販売数量 ) が〇% 下がったので利益が ××× 百万円減って、F( 固定費 ) が〇% 下がったので利益が×× 百万円増加した。その結果、トータルの利益は〇%、×× 百万円増加したという具合だ。
さらに MQ 会計の対前年比の延長上に P( 販売単価 )、V( 仕入単価 )、Q( 販売数量 )、F( 固定費 ) の来期の数値計画を立て、P,V,Q,F ごとの行動計画を策定すると来期の経営計画が出来上がる。この経営計画を毎月フォローし、実績との乖離を指摘し、経営者を励まし、あるいは称賛して背中を押すのが会計事務所の仕事なのだ。
さらに作業の DX 化は大きな効率化をもたらす。
RPAやChatGPT の導入もさることながら、Chatworkは月 1 人 700 円で会社内のみならず取引先を巻き込んで報告・連絡・相談に関わる時間を極端に短縮する。あるいは PLAUD(29 千円 / 台 ) は名刺判の薄い録音機で録音すれば会議でも講演会でも文字起こし、要約、ロジックツリーまで作成してくれる。